父の遺産
プロローグ
時とは、時から逃げ、時を超え、あるいは時に先んじようとする人間にとって、非常に抽象的な観念である。そしてこの柔軟性を持つ時は、私達個人の夢を上空から見下ろし、私達の存在を拘束する唯一のものである。一秒一秒が遺産である。贈与と負債からなる遺産である。人生という砂時計に直面して、その遺産の力を過信してはならない。人は自分の人生を鍛え上げる。と同時に、その人生を耐え忍んで生きてゆく。大切なのは、他人の持つ豊さを汲み取り、他人に自分のそれを与え、人間は一人ではとるにたらないものであり、自身のエコーでしかないと理解することだ。急ぐことも迷うこともなく時と共に生きる人は、調和を見い出し、自分の存在に意義を与えることができる。結局、人は時と共に、一つ屋根の下で生きているのだ。
父の遺産

父は、今朝もいつも通りに起きた。ただ、一大決心を心に抱きつつ。防虫剤の匂いのするたんすの中から、結婚式の衣装を用心しつつ取り出した。グレーのリネンでできた上着、チョッキ、ズボン一式も今となっては四十三年たって、くたびれていた。妻のジャンヌと四十年間、それから心に重くのしかかる苦しみと悲しみと共に一人で過ごした三年間。そしてとある日、心の荷が重くなり過ぎて、あがくのを止めることにした。存在することが空しくなり、以前の人生とはかけ離れたところまで落ちてしまった。現在も未来もない気分になり、父は一番の晴れ着を手にし、背中に走るリウマチの痛みもものともせず身に付け、たんすへと向かった。それぞれの引き出しの中には、彼の人生の一部がしまってあった。一番上の引き出しには、妻の写真。二番目には、領収書の束。三番目の引き出しには、契約書類。一番床に近い、土に近いのが、墓に近付いた時に開ける引き出しだ。その中には、執行官の手による書類が入っていた。結婚証明書、家を買った際の書類、家族手帳、妻の死亡証書。父は家族手帳を手にとった。子供は三人いた。長男のポールは、ふざけてトラックに立ち向かい、近づきすぎてタイヤの下敷きになった。娘のマリ-はある画家に熱を上げ、金持ちの男との安定した生活などには興味も示さず、芸術という運任せの世界に入っていった。彼らの収入は、上下の波が激しく、入ってくるより出てゆく金の方が多かった。でもマリ-の夫は、彼女の事をとても大切にしており、それが一番肝心なことだった。夫がアルコールに目がないのを知っても、マリ-の情熱に変わりはなかった。そして父の目には、それが良い事として映っていた。それから幼年期にとことん甘やかされたシャルル。彼の人生は、はじまりが悪かったと言うしかない。予定より三ヶ月早く子宮から出てきた早生児を、両親は贅沢なプレゼントで覆い尽くしたのだった。その三ヶ月の埋め合わせをするかのように。彼の生き方は以来、顔に表れていた。世の中の貧困には冷ややかな顔を向ける、石の心を持っていた。口座に積み立てられてゆく数字のみが重要だった。まさに精力的な若きやり手幹部そのもので、周りの事など気にもかけずに、やりたい放題生きていた。執行官という職がら、財政難に陥った者の館の錠をたたき壊して入り込む事に喜びを感じ、それを隠しもしなかった。借金に溺れた者の隠し持っていた信じられないようなお宝にありつき、それを奪い取るのを考えては涎をたらしていた。父の事など気にもとめなかった。父の事はマリ-が一切を引き受けていた。
ちょうど曲り角にある石積みの家で、父は街を見ていた。この周辺の地区は、カルチエラタンに似た雰囲気にひたっていた。たこのできた手で長い間つかんでいた家族手帳は汗ばみで湿っていた。もう一度もっと良い解決法があるかどうか自分に問いかけるかのように銀行口座手帳に目を向ける。白内障末期の目で見ても結果は冷酷な程はっきりしていた。そこで悔いのないのを確かめた。
このおしどり夫婦によって長年共有され、振り込みされてきた口座、シャルルが委任状を持っているこの口座は赤字だった。借方に記入された金額にはゼロがいくつもついており、借方最上限額まで膨れ上がっていた。父は一度も息子の良い面を見た事がなかった。さらに歳をとり、月日がたつにつれて、この疑いは強くなるばかりだった。シャルルの教育は大きな過ちだった。野心が大きすぎて、貪欲に常に金もうけをする事しか考えなくなったシャルルは、両親の金をすっかり巻き上げたのだった。年老いた父は、疲れて擦り切れた心臓をさらに締めつけられる思いがした。だが、父としての夢を断念しない事を誓った。子供に大きな期待をかけていた父の夢を。息子の貪欲に限度はなかった。産みの両親の脛をとことんかじって、破産させるところまできた。とにかく金が欲しくて、遺産にまで手をつけていた。そして、これから残りの遺産をたんまり継ぐ事になるのだ。鳥が声を合わせて鳴く中、父は銃を取り出した。妻のジャンヌの写真に最後の一瞥を向ける。もう何も残っていない。時間はせまっていた。息子にひどく哀れな状態まで追いやられてしまった。花との、妻との暖かい約束の時がきた。感情の波打つ大洋にひたりながら父は最後の力を振り絞って指を動かした。引き金にかかった、鉛のように重くなった指の関節が曲がる。それに続いておこった爆音は、外の庭のりんごの木にとまった鳥たちの声に競うかのようだった。失われた存在が一筋、しみひとつないカーペットに流れ出た。
帝国を築く夢は、あっという間にちりとなって崩れていった。少なくともシャルルの頭の中では思い違いがあった。許されるかどうかの保証はないが、父の生前にシャルル次第で許しを求める事もできたのに。今、シャルルは椅子に釘付けにされたかのように、恐れに竦んで座っていた。公証人の事務所に入る前は、もうすぐ享受できる金の事を思って、ほくそ笑んでいた。父の金を貪り尽くした自分は、はした金じゃ満足しないと。後悔が生まれ、今では公証人の言葉を反すうするだけで、身動きすらできなかった。莫大な遺産の夢は、一瞬にして消え去った。頭の中に恐怖がじわじわとはびこっていった。上着の内側のポケットにある財布はすっからかんで、金切り声を出していた。期待していた展開と全く違っているのを理解するまでに時間がかかった。それだけじゃない。模範的な父は何も残さなかったわけじゃなかった。与えられた遺産は、全く息子にふさわしいものだった。相続は伝説となり、後々まで語り継がれるであろう。シャルルにはもう拒むことができなかった。遺言書の開封を承諾する事は、暗黙に借金とその他諸々も受け入れる事を示していた。
この人間的次元でのその他の遺産とは、借金よりももっと重みのあるものだった。口角に玉の汗の浮かぶ、血の気の引いた青ざめた顔で、シャルルは遺書の内容の過酷さに打ちのめされていた。頭髪はすでに白くなり始めていた。大通りにたどり着いた時には、心臓がどくどく打っていた。これだったのか。年寄りを苦しめる胸部の痛みとは!呼吸するのもやっとだった。顔に手をやると、皮膚がしなびてきているのがわかった。肌は黒ずんで、老人特有のシミが手の甲にぽつぽつと表れていた。静脈は浮き出て、打ち身の青あざのようだ。幻覚ではなかった。自分の将来を騙し絵で見ているような気がした。そしてそこに、父の存在を見い出した。顔を殴られたかのように、ハッと気がついた。父からの最後の贈り物とは、これだったのか。遺伝という遺産。つまり自分自身を与える事。シャルルは父の健康状態を財産として相続したところなのだ。なんて贈り物だ。しおれた心臓、長年生きてきて自分の生涯もそろそろページを閉じる時がきたと感じる身震い。光沢のある紙がシャルルの手から滑り落ちた。
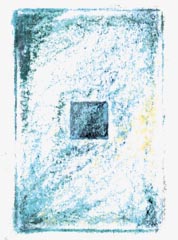
『私こと、マルセル・エは心身共に健全であり、息子シャルル・エに私自身を贈与する事を証明致します。遺産には、私の生理的実体とペースメーカーの受諾も含まれます。つまりシャルルは、私自身の影となるわけです。 ○月○日』
遺書は吹き飛ばされ、排水溝にたまった淀んだ水の中に落ちた。一歩進むごとに背中が曲がってゆくのを感じた。すっかりくたびれていた。うまくはめられた気がした。だが、父の愛よりもすばらしいものなどあるだろうか。心臓が叉ドクンと打った。恨んでもしょうがなかった。金なんてもうどうでもよかった。頭の中で雨が降っていた。このまま気が狂ってゆくのだろう。でもその前に、病人特有の凄まじい速度での老いを知るはめになるのだろう。金に包まれた孤独な男。究極の戦いに負けたのだった。銀行口座にわんさかある金に彼を救えるわけがない。金銭欲が自滅を招いたのだった。

オード・プラケット
1971年生
シャンパーニュ地方、ベルスネー・アン・オットウ在住
フランス文学教授、作家



