冒険
冒険というテーマでものを書いてみる。それ自体がすでに冒険である! なんとかやり遂げられるとしても、出だしはそう楽じゃない。だがくり出してみよう、冒険に。なるようになるだろう!

まず、どの冒険について話すかを明確にせねばなるまい。言葉、特にある物を指すのではなく概念に及ぶ抽象的な言葉は、長い歴史の結果である。言葉は岩のかけらに比べることができる。高い山からはがれてごつごつしていて、なんとも言い様のない形をしている。谷間に転がり落ちてゆき、小川に辿り着き、急流に流されて、角を失い丸みをおびてゆく。他の石にこすられ磨かれて、丸いすべすべした小石になる。それを拾うのは、我々の遠い祖先に当たるもじゃもじゃのヒゲ男だろう。平らな部分のある石だったら研ぎ器に、丸くて握りやすかったら砲弾になるだろう。さらに削られて何かの道具になるかもしれない。1つの石の歴史は長い冒険であり、その時々の使用法によって違った名前で呼ばれることになる。同様に、ヒト科の最初の言葉は平原に響く荒削りな呼び声であった。単に危険を知らせる合図であったり、遠征に出る長についてゆくよう呼びかけるものにすぎなかった。動物だってその程度のことはしていたし、常にしている。アマゾンのジャングルで日の沈むその瞬間、突然至る所からひどく騒々しい鳴き声がしたかと思うと、鳥たちが夜に備えて種別に集まってゆく。そして又突然、元の静けさが訪れる。その鳴き声は、まだ私の耳から離れないほどだ。アフリカザル、コロブの転調するような叫び声も忘れられない。このしっぽの白くて長い、首の周りの白い猿の叫び声は、ある山の頂上から他の頂にまで響き渡る。集まって餌を探しに行く時の合図なのだ。咽頭の目を見張るべき発達のおかげで、数百万年前から人間の叫び声は様々に変化し続け、さらに特徴をもって分化され、様々な種類の人と人との遭遇を重ねながら、発音と意味が地域グループの内部で統一された。丸い小石のように、これらの言葉もそれぞれ調整されてゆく。例外的なのはのちの中国語だ。同国の北と南で文字の発音方法が余りにも異なったものになってしまい、もはや口頭ではわかりあえなくなってしまった。彼らは文字を書きながら会話をする。各文字は中国内どこであれ同じ意味を保っている。そのおかげでこの文明は統一を失わずにすんだのだ。先程話した小石のように、どの言葉もどの言語も、何世紀も続いた冒険の結果なのだ。
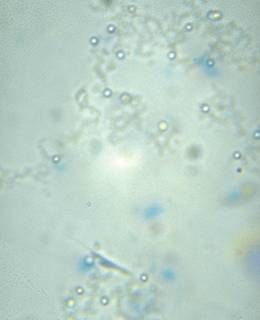
冒険という言葉の意味も他の言葉と同様、何世紀もの間に様々な使用法に適応してきた。よりよく理解するために、この言葉の起源とその使用法を紹介しよう。「アヴァンチュール」はもともとサンスクリット語で「アヴァタール」に近い言葉である。「アヴァタール」はサンスクリットで、グループの庇護を放棄し、そこから離れてゆく個人を示す。又、「アヴァンチュール」という言葉の中には「アヴァン」がある。これはキリスト教典礼暦で、クリスマス前の4週間を示す。これから起こる出来事に考えを向けた待機の期間である。一般的に冒険という言葉は、危険を受け入れながら様々な状況に対処してゆく時に用いられる。どう展開してゆくかが不確かな企てとでも言おうか。さらに冒険という言葉は、以下2つの違った状況に用いられる。1つ目は受け身の状態である。一連の出来事を観察し受け入れるしかない、意表をつくような事態を期待して見ている傍観者である。冒険映画を見に行ったり、推理小説を読む時がこれに当たる。気晴らしになり感動を呼び起こすこともあるが、そこに巻き込まれ、危険にさらされることはない。2つ目の冒険は全く違う基準に基づいている。観察者から当事者にまわり、身を投じる者に関するからだ。この種の冒険は、人間特有なものだ。頭を使って何が待ち受けているのかを考え、危険を推測し、それを受け入れる。危険をおかす価値があると判断した後では、決意も必要となる。傍観者としての冒険は、ここでは精神の冒険となるわけだ。では、冒険という言葉の意味をさらにはっきりさせるために、その様々な使用例を挙げてみよう。このアプローチ方は、中国人が好んで用いる思考方法である。これは概念や物を定義するのに、その機能を説明する方法をとる西洋人とは全く違っている。後者は現代物理のアプローチ方でもある。粒子を識別できたと信じ込み、粒子が実は波動でもあると気がつき、そして変動効果によってのみ観察できるエネルギーをみつけ、安定した快適な空間で、規則的で平和な時間を生きているものと信じていたその頃、アインシュタインが現れた。これまで無関係だと思われていた時と空間の明らかな概念がくつがえされ、実はこの2つは固く結びついているのだと示したのだ。それ以後も我々の感覚、思考は鋭いと思い込んでいたが、絶えずあやまちを積み重ねていっているのにすぎなかった。物質の本質を感知することをあきらめ、結果として数学的体系を想像するのみに留まるようになった。これからの展開を計算によって割り出すのがやっとだった。こうした概念に基づき3000年余りを過ごした後、これらの概念の全側面を検討し、精神の大冒険をした後、結局プラトンの結論に戻ることになる。つまり自分の洞窟の壁に映された影、現実ではあっても近づくことのできない外の世界によって映し出された影の、その先に何があるのかは全くわからないということだ。もしくは仏教的概念にいたって、全ては幻覚にすぎず、天啓を受けて一刻も早くそこから抜け出すしかない、と思うかだ。とにかくこうして長く理屈を述べているよりも、実例を出した方がよっぽどいいだろう。

まず冒険の中でも一番驚くべきものから始めよう。我々が望むか否かにかかわらず、身を投じることになった冒険。すなわち誕生(信仰によっては創造ということになろう)。我々の世界の、生命の、そして人間の誕生だ。先ほど定義した冒険から少し遠ざかった所から始めることになってしまうことは認めよう。これから述べる冒険において、我々は観客にすぎないからだ。しかし創造主の視点に立ってみてはどうだろう。最も危険で最も不可能に近い冒険に、迷わず身を投じた創造主。もともと危険などあり得ない、神は全知であるのだから、と文句を言う者がいるかもしれない。しかし創造主が、宇宙の展開に将来の人間の自由と、偶然の入る余地を導入した際、危険と冒険の概念が再びあらわれる。全能の創造主の全知が実は限られている、という考えはどうだろう。原則としていかなるコミュニケーションもとれない、我々の世界とは違う世界の存在を仮定とする物理学者がいるくらいなのだ。そうでなければ、物理学者よりもずっと権力のある創造主は、空間と時の外側にいながら、最初から全知をもって熟考し、予知できない事や自由のない世界を選ぶことをなぜしなかったのか。では、この冒険がどれだけ途方もないものであるか見てみよう。世界のはじまりに身を置いてみよう。我々が物質と呼ぶものと同時に造られた空間、時が突然ここにある。何十億度にも温度が上がったエネルギーをもつ液体が150億年前に現れ、後に星のきらめく空、氷冠、熱帯林、なだらかな草原、蝶々、そして子供達を生み出すのだ。正に我々は、想像を絶する冒険の証人なのだ。ここまで辿り着く可能性は、ゼロに近かったのだから。ここで少し物理界の歴史に戻ってみよう。この世界はいくつかの基本的な数量に支配され、ミクロン単位からなるものが物質を造っている。生命が誕生するためには、我々の地球が太陽から一定の距離にあり、一定の速度で回転していなければならないことも忘れてはならない。これらの偶然の重なりは信じがたいほどだ。その後の生命の発展は2度目の並外れた冒険である。(完全に無分別とは言えない。我々がこうして存在しているのだから。)それから5億年ほど前、突然生命の誕生が相続き、新しい動物たちの繁殖へとつながっていった。この当時の動物の大部分は子孫をもつことなく消えてゆく。しかし5cmほどの長さの平たいミミズのような「ピカイア」だけが何故か生き抜いてゆく。これが我々を含めた、後に知られる脊椎動物の先祖となるわけだ。もしピカイアが当時の生命体と同じく絶滅していたら、我々は存在しないわけだ。それに続く数億年の間に、4、5回絶滅の危機が訪れた。例えば2億2500万年前、95%の種が消滅した。6千万年前には、巨大な隕石の落下によって物凄いほこりが舞い上がり、地球上は一時闇に包まれた。太陽の光が届かず、凍りつき、植物も草食・肉食爬虫類も姿を消した。隠れていた小さな脊椎動物だけが生き延び、繁殖していった。変化を重ね、数百万年前にヒト科となり、人間となっていった。我々の系列は運命の成りゆきにもてあそばれ、理性的に見たら不可能にしか思えない中を生き延びてきたのだ。全ての生命体の中で今でも存在しているのは、5%にすぎないといわれる。この驚くべき物質と生命の冒険の中で、我々は結果の1つにすぎない。この冒険は前にも言ったように、我々のものではない。危険をおかした創造主の冒険なのだ。

また違った面から、冒険を理解する助けになる例を出してみよう。毎年北極から南極へ移動する渡り鳥たちや、繁殖のために大西洋を横切るウナギたちは、本能のみに従って危険を伴う道を行く。もちろん途中で息絶える者もいるが、危険を予想しはしない。それに比べ、意識の進化した人間にとって冒険は、リスクを負う覚悟さえあれば、本人の認識次第で至る所にある。冒険をするには、数多くの動機がある。例えば発見への情熱、記録への挑戦、名声を得たいという欲望などだ。冒険によって成功をおさめることもあれば、死ぬこともある。いずれにせよ冒険は精神のある姿勢であり、人生を豊かなものにしてくれる。どんな分野にも冒険はある。自分の世界を造り、もっと奥深くへと進みたがった画家、ニコラ・ド・スタエルはそのせいで死ぬはめになる。哲学者ニーチェにしても同じ事が言える。北極地域の海上・海中探検や宇宙探検は、死によって終わることがよくあるが、無事に終わって栄光に包まれることもある。実のところ、危険も友情も愛もない人生など生きる価値があろうか。「恋のアヴァンチュール」を例にとってみよう。頻繁に使われて決まった言い回しになってしまったほどだ。このカテゴリーの冒険には、もちろん危険がつきものだ。しかしここで定義してきた冒険の領域に入るだろうか。情熱が全てを支配する時、危険の概念は存続するといえるだろうか。とすると恋のアヴァンチュールとは、どんな冒険なのだろう。人間は、個人個人が未知の惑星だ。他人の目を通して存在し、自分とは全く違った外観の世界へと辿り着く。もちろん惑星の全てに上陸することはできない。しかし軌道航行が実を結ぶこともある。

私に関していうと、私の人生そのものが冒険の連続だという気がしている。学生の頃は物理に夢中になり、物理学者ジョリオ・キュリーに会いに、規則的にサン・ミッシェル大通りへと足を向けたものだ。彼に付き添ってイヴリ-の倉庫へ行き、人工放射能の最初の実験にも立ちあった。後に原子の大発見に至る世界の初歩に関わっていたわけだ。ジョリオは癌にかかり、早すぎる死を迎える。危険度をはかることなく行っていた実験との関係は否めない。私自身は早い段階で方向転換をしたために、生き残ったのであろう。私は数年後に土木局技師という公務員職をやめ、ルヴァロワのガレージで働き始めたのだった。自分の手を使って働きたかったのと、いくつか免状集めをしたかったためだ。この冒険は程々に成功し、すばらしい体験となった。しかし最初はかなりの賭けであったと言えるだろう。それから憑かれたように旅行に出始めた。世界を知ることになる冒険であった。アメリカ、オーストラリア、アルゼンチンと相次いで長期滞在し、その間仕事とは関係なく、中央アメリカと太平洋の島々へも足を伸ばした。どんな交通手段でもかまわなかった。遠くに行きたいという思いに駆り立てられては、旅に出ていた。気を抜けない時もあったが、良い意味での驚きも沢山あった。残念なことに、パリで仕事を再開し始めなければならなかった。が、今でも旅行はする。絵を描き始めて、多くのア-ティストと出会うようにもなった。そうこうしているうちに、自然の中の人間の位置に対する興味もあって、さらに新しい冒険を始めた。植物学には前々から関心を抱いており、1968年、フランスで植物公園を造り始めた。まだ何を植えるかすら決めずに始めたのだった。この造園という冒険には、30年間、週末の一部を費やした。10年前にはフランス園芸協会の1等賞を受けるという思いがけない喜びにも恵まれた。この公園には2300種の植物が育ち、私にとってパラダイスのような場所になっている。世界を旅行して廻ることもまだやめていない。気の合う友人たちとテントでする旅行ほど楽しいものはない。セルヌッチ美術館友の会会長という役も引き受けた。そのおかげで文化的分野で卓越した人々とつきあうことも出来た。又、長い間日本との事業にも関わっていた。日本の文化、美的感覚と洗練された趣味には感嘆してやまない。

冒険の概念をわかりやすくするために、ここで冒険のもたらす喜びに触れてみよう。数十もあるであろう喜びの中から、いくつかのエピソードを紹介しよう。例えば、中国北京で味わった激しい感動は忘れられない。夏宮での展覧会でのこと。ガラスケースの中には書道の巻き物がひも解かれ、広げられていた。その文字はあまりにも気高く、迷いのない手で書かれており、その美しさの前に、私は感動で胸が締めつけられるような思いさえした。勿論何が書いてあるかは全くわからなかった。衝撃を受けた私を見て、通訳の者が言った。「驚くことなど何もないんです。この文字は今から数世紀前、皇帝によって書かれたものです。おそらく我が国で一番の書道家でしょう。」この日、私は中国の大きさと中国文字の豊かさを本当に理解できたのだと思った。文字はその意味だけではなく、字体によってもその人の考えを伝えるのだ。この時の感動は、私が抽象画をようやく理解した日を思わせる。訪ねていったある有名な画家が、名高い古典イタリアの絵の複製を見せてくれた。彼はそれを裏返しにして掛け直し、言ったものだ。「御覧なさい。主体は消えてしまっても、線と色の全ての調和は傑作のもののままでしょう。」
別の分野に移ろう。かつて船で旅行していた時代は、到着の随分前から大陸の匂いを嗅ぐことが出来たものだ。コルシカ島の潅木地帯のピスタチオの香り。韓国の酢漬けのキャベツの匂い。ブラジルに近づく時は、一種のチョコレートに似た香りがしたものだ。残念ながら飛行機の旅では、この徐々なる接近がなくなり、それと同時に発見に先んじる冒険への夢も薄らいでしまった。オーストラリア沖でスキューバダイビングをしたことも思い出される。巨大なイカがどこからともなく私の正面に現れた時の事は、今でも忘れられない。ゆらゆらと浮かぶその姿は、真珠のような光沢を放ち、太平洋の暗くて青い奥底から出現した冷光のようでもあった。別の機会には、それが何かを見る前に何かを感じてビクッとしたことがある。コバンザメが私を鮫だと思って、突然ももに張り付いてきたのだった。危険はないとわかっていても、私は無人島沖で一人きりだったため、心穏やかではなかった。そして鮫との出合いは、時にはかなり不安になるものであった。

しかしさらに興味深いのは、驚くべき人々との出会いだ。例えば、ヒマラヤ山脈に住むヒンズー教徒の隠修道士、もしくはセヴェンヌ山脈の人目につかない場所で暮らすフランス人隠者。又、プレー山の動きを監視する役を引き受けた少し向こう見ずなフランス人火山学者の事も覚えている。非現実的な風景も頭に焼き付いている。天国ではないかと思えるような色を造る日没や日の出。星のちりばめられた夜空の下で広がる金色のビロード砂漠。日の光と共に現れる穢れのない波打つような砂丘。その頂を超えてみたいと思う気持ちは押さえきれない。アフリカではすばらしいマサイ族の人々と出会った。星の下で歌い、踊っていた彼ら。禅宗やその他の仏教の僧侶たち、道教の道士たち、神道の神官たち、バラモン教の僧たち、フランスやそれ以外のべネデイクト会修道士たちのことも良く覚えている。歌い、祈り、目に見えない何かに少しでも近づこうとしていた彼らであった。
我々の大地はすばらしい。人間はそれよりさらにすばらしい。こうしたこと全てをよく理解するには、考えるよりも感じる方がいい。「コンプラーンドル(理解する)」という言葉は、「カム プレエンデール」から来ている。吸収する、抱擁する、しみ込むという意味だ。通り過ぎる風、視線、匂い。全てにアンテナをはっていなければならない。冒険とは、計量しきれないものだ。どこか常軌を逸しているが、その無分別さがなければ、遠くへは行けない。冒険とは、私の目の前を通って遠くまで流れてゆく、滑らかなビロードでできた大河のようなもの、とでも言ったらいいだろうか。そして、おそらく少し行ったかすんで良く見えない辺り、思いがけないような所で、ほのかな光が現れることもあるだろう。そう、人魚は本当にいるのである、、、ただ、人魚と我々を隔てる空間に、危険がないわけではない。しかし誘惑に抵抗しようとしても無駄だ。幸せは、ビロードの大河沿いに、そしてその先にあるのだから。
ユベール・トゥルイユ伯爵
1919年パリに生まれる。
セルヌッチ美術館友の会名誉会長、三越フランス前会長。
パリ及びブロワ近郊のオルシェーズ修堂分院に住む。

書斎にて、次なる冒険を熱く語るトゥルイユ氏。
そのきらめく好奇心の瞳は少年そのものだ。
背面の陳列棚には、旅の先々から持ち帰った、蝶、昆虫、不思議な模様の石、、、などが息をひそめている。





