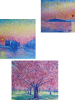顔の情熱

「冒険」に続き、『Pont』の最新号は「gout(グ)」をテーマに掲げて編集される。gout(グ)ということは好みや魅力に関係することである。言葉の本来の意味では食べ物、ワインなどの「味」という意味であるが、より広い意味では活動、スポーツ、芸術などに対する「趣味」という意味で用いられる。そこで私はいくつかの趣味、というよりは私の好み、何というか、私が魅力を感じる顔、顔に対する情熱について話してみたいと思う。
とにかく私はデッサンするのが好きだった。辞書の欄外や、レストランの紙のテーブルクロス、もちろん直接テーブルの上にまで、いたる所に始終落書きするタイプの少年だった。夢中になってデッサンしている時、突然誰かに鉛筆を取り上げられ、夢から引きずり出された少年は、面食らって「なに?」ということ言葉を投げつけたこともある。
青春時代に、最初の絵との出会い、最初の強烈な感動:グレコの見知らぬ騎士、ファイユームの肖像画、レンブラントの晩年の自画像、そしてもう一枚、13歳のデュラーの自画像(その時、私も13歳だった。450年前に描かれたこの顔、にもかかわらず永遠に若いこの顔、じっと見つめているうちに、私はふと目まいに襲われた)。この時から、顔に対する私の好みが、巨匠たちの傑作によって偶然にも裏付けられたのである。これらの絵はもちろんモデルに類似した肖像画だった。しかし特に、巨匠たちは私を画中の人物の精神生活に引き込んだ。私は、無意識のうちに、絵の世界に生きていた。その中で偉人たちは口をそろえて、「続けよ」、と私に言った。

私は類似性を求めずに、イマジネーションで顔のデッサンを描き続けた。時には、道路やメトロの中ですれ違う通りすがりの人からヒントを得て。数メートルの距離からみた彼らの眼差しは、もはや点でしかない。時にはまた、どこから引き出したのかわからない、自我の奥底に潜んでいる何か一精神分析学者がイド*(ça)を改名することに深い喜びを感じると私は確信している一から引き出してきて。
いつも小さなサイズで、デッサンや絵を素早く制作する。そうすると、少なくとも私にはそう思われるのだが、私が主題と保つ生(なま)で、直接的で、ほとんど感情的な表現をうまく絵にすることができるのである。どうして私がいつも両眼から始めるのかは聞かないでいただきたい。
私は新しい作品に取り掛かる度に、その都度、実際に出会った顔やちらっと見た顔の秘密を理解しようとし、その顔を生き生きさせている情熱を再現しようとする。私の家族や友人に言わせると、私の作品は20年代のドイツ表現派の画家たちに似ているということだ。
墨、グワッシュ、油絵具などいろいろなテクニックを使って、数十年来、描き続けてきた。年とともに、作品は私の人類に対するビジョンを表現する一方、私の個人的な気持ち、私の幸せな体験・不幸な体験を表す一種の私記のようなのものになった。50年代、60年代のビジョンは、どちらかというと悲観的なものだった。私はその頃、顔、もっと正確にいえば深刻で、苦しみあえぎ、激しく攻撃的な「表情」を描いていた。黒が色彩に取って代わった。
その後、穏やかな顔つきになり有彩色が再び使われ出したが、なお顔は不可思議で、物問いたげで、両眼は常によそ、地平線の方、あるいは一種の理想郷に注がれている。あるいはまた私たちを見ている。私たちを注意深く観察していて、人生というものの意味や、彼らの人生の意味や、我々の人生の意味について我々に問い掛けているようでもある。
*フロイトの理論において、自我 moi、超自我 surmoiとともに精神の一部をなすとされる無意識的エネルギー(訳者注)
フィリップ・ネルー
画家
1930年生まれ
パリ・外国にて展覧会
サン・モール・デ・フォセ(ヴァル・ド・マルヌ県)在住